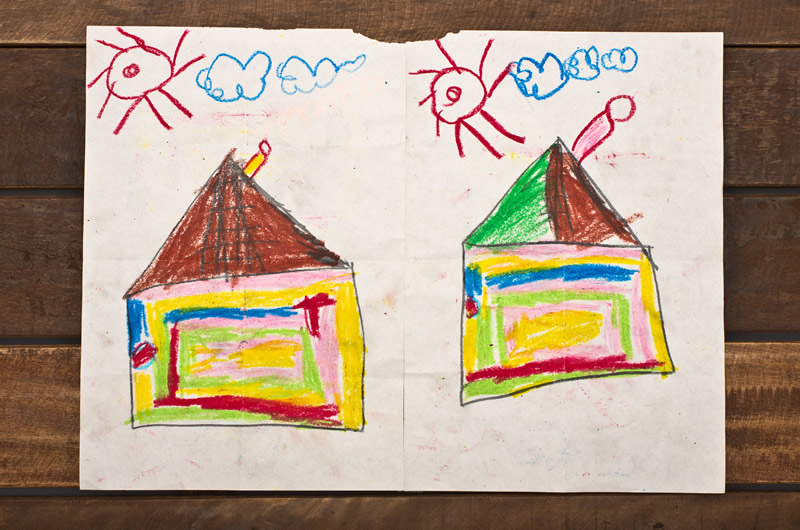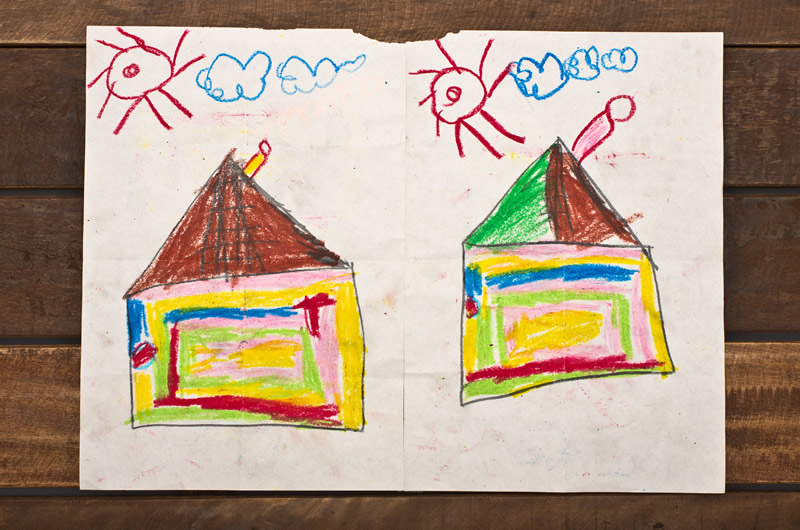もうすぐ3月だけど、まだまだ寒~い日が続いている信州です。
そんな中、お隣の山梨にあるフルーツ公園へ行ってきました。
この公園は山の上の方にあって、新日本三大夜景になるほどのとっても眺望がよい場所です。
(今の時期はハウスでいちご狩りができるみたい。)
その公園内にあるトロピカル温室に行ってきました。
外からみても南国っぽい雰囲気がプンプンしててテンションも上がります♪
中は外とは違って暖かくって濃淡のブーゲンビレアの花もいっぱい咲いていて綺麗でした。(^_^)
↑コーヒーの木もあってたくさん実がなっていました。 ほーんのりコーヒーの香り♪
それから、卵の木ですって。上からビヨーンと枝が垂れ下がっていて大きめの卵のような実が育っていました。
食べれるのかナ?
この鳥みたいな花↑・・・『極楽鳥花』というそうです。おもしろい(^-^)
他にもマンゴーやパパイヤや椰子の木でワサワサしている温室内をあっちいったりこっちいったりしながら楽しめました。
公園から車でどんどん上っていくと、『ほったらかし温泉』があります。名前がいい(笑)
天気が曇りだったので富士山は見えませんでしたが、山の上の露天風呂は最高!でした。
『あっちの湯』と『こっちの湯』があって、今日は『あっちの湯』に入りました。
気持ちよかったー。
朝6時から営業していて(現在)、美しい日の出は見れるし、夜は夜景も楽しめるし、混み込みの人気温泉っていうのもうなづけます。
もうすぐこの辺りも桃の花で満開になるんだろうなぁ~。
花もいいけど、桃狩りやぶどう狩りの季節にも来て見たいです。